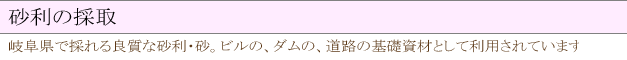
砂利は採取場所によって、河川砂利、陸砂利、山砂利、海砂利の4種類に分かれます。岐阜県では、海砂利を除く河川砂利、陸砂利、山砂利の3種類を採取しています。特に、木曽川、長良川、揖斐川、の3河川流域と飛騨地区で良質の河川砂利、陸砂利が、また、土岐丘陵より山砂利が採取され、基礎資材として良質な砂利を供給しています。 (参考:岐阜県砂利採取マップ)
■砂利の種類
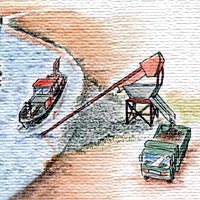 |
河川砂利 川からとれる砂利で、下流に行くほど丸みを帯び、小さくなっています。 |
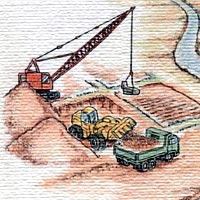 |
陸砂利 かつて河川敷だった田んぼや畑、平地林から採れる砂利。 |
 |
山砂利 地殻変動で隆起し、今は山となっている所から採れる砂利。 |
| 海砂利 海中から採れる砂利。 |
■陸砂利採取の流れ
| 表土剥離 |
||||
 |
→ |  |
||
| 耕作土剥離 | 耕作土堆積 | |||
安全施設等設置 有刺鉄線柵は1.2m以上で5段張り以上、トタン板柵は1.8m以上で適度の間隔でのぞき窓を設けます。 |
||||
 |
||||
| 周囲外柵取り付け | ||||
採掘 作業上の安全性の確保のため、また隣接地への崩壊の防止等、災害防止のため安定した法勾配で採取します。 原則として隣接境界より2m以上離れた地点で採掘を行います。 採掘深5mを超える場合においては、5m以上保安距離を保ちます。 |
||||
 |
||||
| 砂利採掘 | ||||
埋め戻し 埋め戻しの材料には山土および良質な公共用流用土等、農地として使用し得る適切なものを用います。 また地下水に悪影響を及ぼさないものを使用します。 産業廃棄物等は一切埋め戻しに使用しません。 |
||||
 |
||||
| 埋め戻し | ||||
整地 山土基盤をしっかり転圧し、基盤が下がらないようにします。 耕作土はある程度乾燥した状態で石が混じらないように整地します。 原則として 、採取前と同じ原形復旧とします。 |
||||
 |
→ |  |
||
| 床上整地 | 耕作土整地 | |||
引渡し |
||||
 |
||||
| 復元引渡し | ||||
■砂利・砂採取は、農地改良や水流調整、美観維持にも貢献しています。
![]()
骨材の年間需要量6億トンという現実の数字は、わが国で生産される工事用原材料のうち最大量を占めています。このことからも骨材生産が国民生活へ与える影響の大きさを、伺い知ることが出来ます。
こうした膨大な需要を賄っている骨材の約半分が天然の砂利・砂で、更に約半分が、現在、平地で田や畑になっている部分から採取される陸砂利と、河川敷内の河川砂利です。そして陸砂利採取跡は新しい土壌が入れられ、農地改良に寄与しているし、河川砂利の採取は、河川管理事業と併行して行われ、水流調整や美観維持の役割を果たしています。また、建築用の良質な砂は山砂等により供給され、その跡は植栽によって緑の保全がなされている、などという事実は、社会的にあまり知られていません。
農地や河川の管理、林地保護などの施策は、必要かくべからざるところです。しかし砂利採取事業が、それらを阻害するものでないばかりか、影の支援活動の一翼を担っているのです。